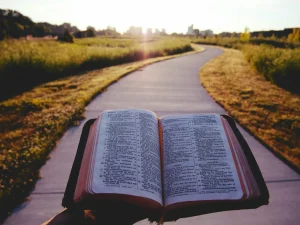「そういう人たち」は信者か未信者か
(へブル6章4~6節)
前田大度

一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊にあずかる者となって、神のすばらしいみことばと、来たるべき世の力を味わったうえで、堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自分で神の子をもう一度十字架にかけて、さらしものにする者たちだからです。(へブル人への手紙 6章4~6節)
この非常に厳しい警告は、誰に対して発せられているのでしょうか。『ライリー・スタディ・バイブル』の解説は三つの見解を挙げています。
(1)アルミニウス派は、ここに書かれている人々は実際に救いを失ったクリスチャンだと考える。もしそうなら、この箇所はもう一度救われることが不可能だと教えていることになる。
(2)ある人々は、この箇所は真実な信仰者のことではなく、単なる信仰告白者のことを述べていると考える。それゆえ、4-5節は救いに至らない経験だと理解される(9節参照)。「堕落」とは真理の知識から離れ去ることであって、真理を個人的に所有していたわけではない。
(3)他の人々は、この箇所を、クリスチャンの成長と成熟を促すための、真実な信仰者への警告と理解する。「堕落」は不可能だが(この見解によれば、真実な信仰者は永遠に安全だから)警告を強めるためにこのフレーズが文中に置かれている。ちょうど先生が学生たちにこう言うのに似ている:「皆さんがこのコースに一度登録した以上、たとえ時計の針を戻せたとしても(それは実際には不可能なので)コースを最初からやり直すことはできません。ですから、学生の皆さんはより深い知識へと進みましょう。」この見解では、4-5節は回心の体験を指すと理解される。「光に照らされる」(10:32)、「味わう」(2:9)、「あずかる者」(12:10)という語が、ヘブル書の他の箇所で、真実な経験について使われている点に注目せよ。
(1)の見解は、救いの安全性を明確に述べている聖句と矛盾してしまうので間違いです。例えば、以下の聖句は救われた者が救いを失うことがないことを明瞭に保障しています。
わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは永遠に、決して滅びることがなく、また、だれも彼らをわたしの手から奪い去りはしません。
(ヨハネの福音書 10章28節)
私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
(ローマ人への手紙 8章38、39節)
あなたがたを、つまずかないように守ることができ、傷のない者として、大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して、栄光、威厳、支配、権威が、永遠の昔も今も、世々限りなくありますように。アーメン。
(ユダの手紙 24、25節)
ライリーは(3)の見解のようですが、はたして「4-5節は回心の体験を指すと理解される」でしょうか。ヘブル6章4節と5節の人の、5つの特徴を順に検討することにします。
1.「一度光に照らされ」
同じ表現は10章32節でも使われていて、そこでは明らかに信者を指しています。
あなたがたは、光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた、初めの日々を思い起こしなさい。
光に照らされるとは、人が聖霊によって霊的な理解力が与えられることを意味します。それゆえ、信者は全員、光に照らされた者たちですが、光に照らされた者が全員信者になるわけではありません。重要なのは、光に照らされた人が、その光に応答し、光を信じ受け入れるかどうかです。
「自分に光があるうちに、光の子どもとなれるように、光を信じなさい。」
(ヨハネの福音書 12章36節)
2.「天からの賜物を味わい」
「味わう」とは「経験する」ことを意味します。口に入れて味わうだけで飲み込まない、という意味ではありません。ヘブル2章9節では、主イエスが十字架の苦しみを経験されたことに「味わう」という語が使われています。
イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。
「天からの賜物」とはキリストご自身です。主イエスがどれほど素晴らしい方であるかを、みことばや信者の証しを通して味わうことは、未信者でも可能です。
3.「聖霊にあずかる者となって」
この表現が聖霊を受けた信者であると理解する人々は、次の聖句を根拠にして「キリストにあずかる者」が信者を指す以上「聖霊にあずかる者」も信者だと言います。
私たちはキリストにあずかる者となっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、です。
(へブル人への手紙 3章14節)
しかし「キリストにあずかる者」の「キリスト」には冠詞がついていますが、「聖霊にあずかる者」の「聖霊」には冠詞がついていません。この違いは重要です。聖霊に冠詞がついていないということは、ここでは聖霊ご自身を指しておらず、聖霊の力や働きを指しているということです。ですから「聖霊にあずかる者」もまた、光に照らされた者と同様で、すべての信者は、救いへと導いてくださる聖霊の働きにあずかったからこそ、キリストを信じて救われましたが、聖霊の働きにあずかった者が全員、救われるわけではありません。
4.「神のすばらしいみことばを味わった」
この「みことば」は、語られたみことばを意味します。つまり、この人はクリスチャンの集まりに参加し、神の愛と恵みのメッセージを聞いたのです。「信仰は聞くことから始まります」が(ローマ10:17)、「私たちが聞いたことを、だれが信じたか」(ローマ10:16)とあるように、聞いたことを信じなければ救われません。
5.「来るべき世の力を味わった」
「来るべき世」とは千年王国のことであり、「力」とは奇跡を意味します。ヘブル人への手紙の読者たちは、主イエスや使徒たちを通して行われた、様々な奇跡を経験しました。
このように、へブル書6章4-6節の人は信者だと聖書から断定することはできません。彼らは福音の理解力が与えられ、キリストのすばらしさを味わい、聖霊の導きにもあずかり、神のことばを喜び、様々な奇跡をも体験しましたが、救いには至らなかったのです。
また、ヘブル6章4-6節の人には、確かに救われた信者だけに用いられる表現が使われていません。すなわち、新しく生まれた、神の子どもとされた、永遠のいのちを受けた、御霊を受けた、御霊によってバプテスマされた、御霊の内住を受けた、聖徒とされた、などの決定的な表現がありません。すなわち、この人々は、悔い改めを伴う真実な信仰には至らなかった人です。