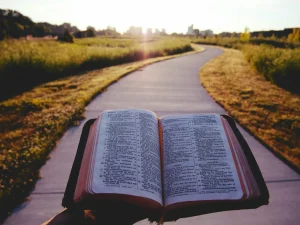使徒時代以降の教会における
異言の賜物
(A.D.100-400年)
クレオン・L・ロジャーズ・ジュニア
(Cleon L. Rogers, Jr.)
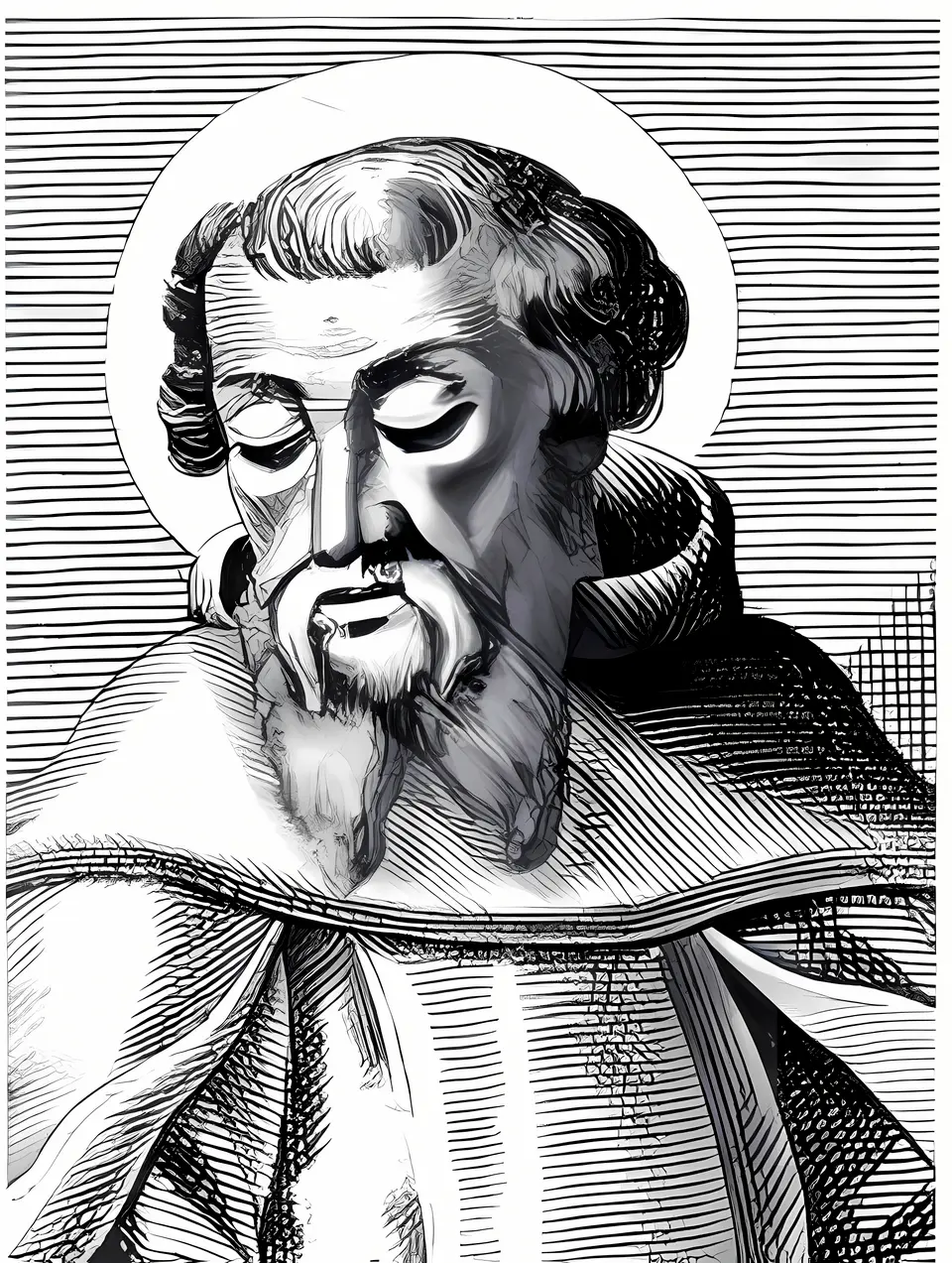
パウロの教えの中で、異言がやむべきものであることは明白だが(1コリント13:8)重要な問題は、異言がやむのはいつかということである。本論文は、この疑問に対する可能な答えを議論することを意図しているのではない。むしろ使徒たちの時代と同じように、異言がいつまで実践されていたかどうかを判断するために、紀元100年から400年までの教父たちの証言を検証することを目的としている。もし異言の賜物が1世紀に完全に途絶えていなかったとすれば、その継続の証拠があるはずである。多くの人々が教えているように、異言の賜物が重要であるなら、使徒時代以後の指導者たちは異言について強調し、その実践を大いに称賛したはずである。しかし、紀元100年から400年までの教会において、異言が重要な位置を占めていたことを示す証拠はない。
使徒教父の証言
使徒たちの時代に異言の賜物が実際にあったことは、聖書からの明らかな証拠がある。しかし、使徒教父たちの著作には、この賜物に関する言及、暗示、記述が一切見られないという点は重要である。これは単なる「沈黙からの論証」であり、異言の継続を支持するものであると同時に、異言の消滅を支持するものでもある、と反論されるかもしれない。しかし、この沈黙の重要性は、ある事実に照らすと、さらに重みを増す。
第一に、使徒教父の何人かは、使徒たちの時代に賜物が実践されていた教会から、あるいは教会に向けて書いている。その最も顕著な例は、ローマのクレメンス(AD.35-101)の『コリント教会への手紙』である。異言が実践されていた初代教会があるとすれば、それはまさにここである。しかし、ローマのクレメンスは、彼らの霊的な遺産について語るときでさえ、この賜物について一言も触れていない。権威への不従順という同じ問題は存在したが、異言の問題は異言の停止によって明らかに解決されていた。イグナティオス(AD.35-107)は、最初のクリスチャンが異言を話したエペソ教会に(訳者注:使徒19:6のこと)手紙を書いたが、彼もまた異言の賜物について何も語っていない。
第二に、使徒教父たちの地理的範囲が広いことが、彼らの沈黙を重要なものにしている。クレメンスはローマからコリントに手紙を書き、スミルナの司教ポリュカルポス(AD.69-155)はピリピの人々に手紙を書き、アンティオキアのイグナティオス(AD.35-107)はエペソ、マグネシア、トラレス、ローマ、スミルナ、フィラデルフィアの教会に手紙を書き、バルナバの手紙はおそらくアレキサンドリアから書かれた。『ヘルマスの牧者』はローマから書かれた可能性があり、パピアス(AD.60-130)はフリギアのヒエラポリスから、『ディダケー』はエジプトから、あるいはシリアかパレスチナから書かれた可能性があり、『ディオグネトスへの手紙』はおそらくアレクサンドリアから書かれた。もし異言の賜物が広範かつ豊富にあったなら、何らかの形で言及されるか、言及されたに違いない。
第三に、使徒教父の教義的性格から、異言に関する沈黙は重要である。彼らの著作は神学の教科書として書かれたわけではないが、新約聖書で教えられている主要な教義をほとんど網羅している。神論から終末論に至るまで、すべてについて言及されているが、異言について論じた形跡はない。
第四に、多くの著作の目的が異言の省略を重要なものにしている。例えば『ディオグネトスへの手紙』の目的は、キリスト教に関するディオグネトスの疑問に答えることであった。筆者は、偶像礼拝の愚かさ(1-2)、ユダヤ教の不十分さ(3-4)、キリスト教の優位性(5-12)を示しながら話を進める。これは、キリスト教の超自然的な性格を証明するものとして異言の賜物を提示する絶好の機会であったろう。前述のように、ローマのクレメンスはコリントの霊的誤りを正すために書いたが、異言については何も述べていない。エイレナイオスは、ポリュカルポスのピリピの信徒への手紙について、「そうすることを選び、自分の救いを心配している人々は、彼の信仰の性格と真理の宣教を学ぶことができる」と述べている。しかし、ポリュカルポスは異言がキリスト教の正常な性格の一部であることをどこにも示していない。
以上の考察から、使徒教父たちの沈黙には何の意味もないと、単純に片付けることができないことは明らかである。
殉教者ユスティノスの証言
紀元100年頃に生まれ、紀元163年から167年頃に殉教したユスティノスは、ローマ帝国を広く旅し、異言を語る現象に接したはずである。彼はサマリアで生まれ、エペソで回心し、キリスト教の教師として帝国中を旅した。このような広範囲な旅と教えにもかかわらず、ユスティノスは異言の賜物について何も語っていない。
しかし、彼の著作『トリフォとの対話』の中に、ユスティノスが異言を知っていたと思わせる箇所がある。ユダヤ人の預言者の賜物がキリスト者に移ったことを論じる中で、彼は次のように述べている。「それゆえ、あなたがたは、かつてあなたがたの民族の間にあった(賜物が)私たちに移ったのだと理解すべきである。」しかし、ジャクソン(Jackson)は「異言を語ることがここで意図されているかどうかは定かではない」と指摘する。これを裏付ける根拠はいくつかあり、ユスティノスが異言の賜物を念頭に置いていなかったことはほぼ確実である。第一に、ユスティノスは、彼が語っている賜物は、以前はイスラエルの民の間にあったと述べている点である。なぜなら、異言の賜物は教会に関連してのみ用いられるからである。第二に、ユスティノスは賜物について語るとき、7つの賜物を挙げているが、異言の賜物は含まれていない。これらの事実に照らせば、ユスティノスが異言の賜物を念頭に置いていなかったことは明らかである。
使徒教父たちの沈黙が重要であったように、殉教者ユスティノスの沈黙も重要である。ユスティノスが広く旅をしていたにもかかわらず、異言に言及していないという事実は、彼が異言現象に遭遇したことがなかったか、遭遇したとしてもその賜物に感銘を受けなかったことを示している。もう一つの事実は、彼がキリスト信仰の教師であったにもかかわらず、異言はキリスト信仰の教理の不可欠な部分でも重要な部分でもないと、沈黙によって示していることである。もし異言が重要な賜物であったなら、なぜ彼のように著名な人物がこの賜物について何も言及しなかったのだろうか。
ユスティノスの沈黙に重みを与えているもう一つの事実は、彼の著作の性質である。彼は『トリュフォンとの対話』の中で、ユダヤ教に対するキリスト教の優越性を示している。これは異言の賜物について論証する絶好の機会であっただろう。ギリシア人への護教的著作を書いたとき、彼はキリスト信仰と異教とを正確に検証すると明言している。両者の教えを比較することによって、キリスト信仰が真の信仰であることを証明すると述べている。異言の賜物というのは、彼が最も強く用いることのできるものの一つであっただろうが、彼はそれについて言及さえしていない。
エイレナイオスの証言
エイレナイオス(AD.130-202)の証言は非常に重要である。なぜなら、異言に関する彼の発言は、使徒たち以後の数世紀における異言の賜物の存在を示す証拠として指摘されてきたからである。エイレナイオスは、「私たちは、教会で多くの兄弟たちが、御霊によってあらゆる種類の言語を話すのを聞いている」と述べている。この記述を詳しく検討する前に、エイレナイオスの背景を調べる必要がある。エイレナイオスの生い立ちについてはほとんど知られていないが、わずかに残っている情報は非常に重要である。スミルナで育った少年時代、彼はポリュカルポスの話を聞き、彼から大きな影響を受けた。紀元177年頃、エイレナイオスは小アジアからガリアのリヨンに渡り、ポティヌスの下で司祭となった。この間、彼はリヨンで激しい迫害を目撃し、誠実な友人であったポティヌスが残酷に殺害されるのを目撃した。まだ長老であった彼は、司教エレウテロスに宛てた手紙を持ってローマに送られた。この手紙は、モンタヌス派の一団が、エレウテロスに自分たちに好意的な態度をとるよう説得するために書いたものだった。ポティヌスの死後、エイレナイオスはリヨンの司教となり、彼も殉教の死を遂げるまで仕えた。
本研究に関連して、エイレナイオスの背景には二つの点がある。第一に、彼は小アジアから来て、リヨンで奉仕した。小アジアとシリアでは、キリスト教に多くの不健全な影響、特にモンタヌスとその誤った聖霊論の影響があったことを理解することが重要である。エイレナイオスがリヨンに到着しても、モンタヌス主義者との関係は絶えることはなかった。小アジア出身のポティヌスとエイレナイオスに加えて、フリギア出身のアレクサンダーとペルガモン出身のアッタロスもリヨンに滞在していた。このような密接な関係から、良い意味でも悪い意味でも、精神的・教義的なつながりがあったのは当然のことであり、モンタヌス主義はリヨンの悪い要素の一つであった。異言に関するエイレナイオスの発言は、このような観点から見るべきものである。彼はその背景から、モンタヌスの影響を受けた人々の霊的な行き過ぎを聞いていたことは明らかである。
エイレナイオスの背景について観察すべき第二の点は、彼がポリュカルポスの影響を受けていたことである。この密接な関係から、彼がキリスト教の教義に関する知識の多くをスミルナのこの老司教から得たのは当然のことだろう。ポリュカルポスの著作に異言が含まれていないことは明らかであり、エイレナイオスの神学の大部分を異言が占めていないことはさらに重要である。もし異言が非常に重要であるなら、師も弟子もそれを強調したはずである。
しかし、彼らはそうしなかった。以上のことを念頭に置いて、エイレナイオスの異言に関する記述を吟味してみよう。
第一に、エイレナイオスは自分が異言を語ったとは言っていない。
第二に、彼は「私たちは聞いている」と複数形を使っていることから、彼の近くにいる人々を異言の賜物を持つ者として分類していないことが明らかである。コクセ(訳者注:英国の歴史家 Coxe)は、古いラテン語では「私たちは聞いた」という完了形[audivimus]が使われていることを指摘している。第三に、エイレナイオスはモンタヌス派と関係があったので、ロバートソンの言う通り、「彼の曖昧な記述は、小アジアのモンタヌス派に関する何らかの報告に基づいているのかもしれない……」。これらのことから、エイレナイオスの発言は、彼や彼の周囲の人々が、モンタヌス派の人々の間で伝えられていることを、過去のある時期に聞いたことがあるという意味であったと結論せざるを得ない。エイレナイオスの著作全体について言えば、確かに彼の神学の主眼と重点は、異言の賜物にはなかったと言える。
テルトゥリアヌスの証言
北アフリカの著名な神学者テルトゥリアヌスもまた、モンタヌスの影響を受けた一人である。彼は広く旅をし、傑出した学者であったが、異言の賜物に関する言及は少なく、モンタヌス主義との関係を裏付けている。魂が一種の身体性を持っていることを示そうとして、彼は魂の属性について述べているが、そのひとつが霊的な賜物を持つ能力である。
この点を説明するために、彼は天使と会話したり、その他の恍惚体験をしたというモンタヌス派の女性の例を挙げている。異言の賜物については言及していないが、「啓示の賜物があり、聖霊によって恍惚的な幻視を体験する……」と表現している。もしこれが賜物の活動に対する証しであるとすれば、それは弱い証しであり、当時の通常のキリスト教的体験からかけ離れていることは確かである。
テルトゥリアヌスは『マルキオンへの反論』の中で異言の賜物について具体的に言及している。ここでも彼は、当時の異言については何も語っていない。彼はパウロの書簡を取り上げ、それぞれの書簡に見られる弁証的価値を指摘している。彼は書簡を一通一通、章ごとに取り上げている。第1コリント12章から14章に述べられている霊的賜物については、すべての人が同じ賜物を持っているのではなく、御霊が人によって異なる賜物を与えていることを認めている。彼は、パウロが賜物について述べていることを論じるだけで、彼の時代における賜物の使用については言及しない。彼はマルキオンに対して、使徒たちが示したこれらの賜物を複製するよう求めているが、自分がその賜物を行使する者を見たとも知っているとも言っていない。
モンタヌスの証言
異言の現れに関する唯一の明確な記述は、モンタヌスの活動に関するエウセビオスの記述にある。そこには、モンタヌスが「魂を奪われ、突然、錯乱と恍惚の状態に陥った。彼は取りつかれたようになって奇妙な言葉を発し始め、初代から代々伝えられてきた教会の言い伝えと慣習に反することを預言した」とある。「異言」という言葉は明白に使われていないが、リーツマン(Lietzmann)が指摘するように、モンタヌスがその体験の中で「グロッソラリア(意味不明な発声)の特徴をすべて示した」ことは明らかである。モンタヌスの証言の意義は以下の点である。第一に、彼は異端とみなされた。彼は聖書に従わず、周囲の人々もそれを認めていた。第二に、彼が特に異端とされたのは、聖霊論の領域と、この賜物の強調であった。しかし、このような強調にもかかわらず、モンタニストの活動は使徒たちが行使した賜物にははるかに及ばないと考えられていた。第三に、リーツマンは、この恍惚状態と意味不明な発声という現象が、当初は急速に広まらなかったと指摘している。これは、このような極端な現象が通常のキリスト信仰の体験の一部でないことを示しているように思われる。もしこれが一般的な習慣であったなら、多くの人がこれを通常のクリスチャン生活の一部であると、もっと自然に受け入れたはずである。
オリゲネスの証言
オリゲネスの神学のすべてが正統的とは言えないかもしれないが、彼が当時最も優れた学者の一人であったことは誰もが認めている。彼は幅広い読書を通じて当時の事情に通じていただけでなく、自らも広く旅をし、世界中から生徒を集めて教えていた。もし異言が広く行われていたなら、オリゲネスはそれについて何か知っているはずであり、彼の膨大な著作のどこかで触れているはずである。しかし、彼はこの賜物について明確な記述をしておらず、彼の証言によれば、特別な賜物はなくなっていた。
オリゲネスは『ケルソス駁論』の中で、霊的賜物について言及している。ケルソスは、旧約の預言者たちがフェニキアやパレスチナの一部の者たちと同じように、愚かな身振りや動作をしてから「預言」を語ると非難している。オリゲネスが引用するケルソスの言葉によれば、「これらの約束には、奇妙で熱狂的で全く理解不能な言葉が付け加えられている。それは理性的な者には全く意味が分からないほど曖昧であり、結局、愚か者や詐欺師が自分の目的に合うように勝手に解釈する口実を与えるものに過ぎない」という。
この批判に対するオリゲネスの反論は、まさにこの議論に関わるものである。彼は、キリストの宣教の初期や昇天後には聖霊がその臨在を示すためのしるしや外面的な証が与えられていたが、それらは次第に減少し、もはや広く行われてはいないと述べている。さらに彼は、ケルソスが人から聞いた話をもとに述べていることは偽りであり「ケルソスの時代には古代の預言者に類する者は現れていない」とも述べている。つまり、オリゲネスは、彼の時代にはこれらの賜物がもはや機能していないと明言しているのである。彼は異言の賜物が彼の時代に繁栄しているとは言っておらず、むしろそのような賜物は衰退したと述べているのだ。
クリュソストモスの証言
教父の最後の一人は、優れた聖書解釈者であり、優れた説教者であったクリュソストモス(AD.347-407)である。クリュソストモスはアンティオキアで学び、宣教した後、コンスタンチノープルの総主教となった。コンスタンチノープルという大都市の宗教指導者として、彼は帝国中のキリスト教徒や教会と接触していたに違いない。コリント人への手紙第一の霊的賜物に関するメッセージの中で、彼は「その場所全体が非常に不明瞭である」と告白し、さらにこう付け加えている。「しかし、その不明瞭さは、言及されている事実に対する私たちの無知と、当時は起こっていたが今は起こらなくなったような、その事実の消滅によって生じたものである」。これは、4世紀の博識で宗教的指導者であった人物が、彼の時代には異言はもはや行われていないと明言しているのである。キリスト教界では、異言の賜物は普通のことではなく、むしろ知られていない! クリュソストモスの地位と立場は、彼の証言を極めて重要なものにしている。少なくともこの時代には、異言の賜物は消滅していたことは明らかである。
一般のクリスチャンの証言
ある人は、これらの人たちは神学者であり、教会の指導者であって、一般のクリスチャンの特徴を反映していないと反論するかもしれない。教会の指導者たちが異言のような現象を見過ごすことは考えられないが、専門的な護教論者の中には、一般的なクリスチャンの真の姿を反映していない者がいるかもしれない。しかし、カーペンター(Carpenter)は、2~3世紀の一般的なキリスト信仰を反映しているのは、まさに使徒教父たちであると指摘する。先に述べたように、使徒教父は異言についてまったく言及していない。パピルスに残されている一部の初期キリスト教徒が用いた秘儀の言葉でさえ、意味不明の言葉はあっても、異言の賜物とは類似していない。
結論
西暦100年から400年頃にかけて、ローマ帝国のほぼ全域で活動した初期のキリスト教指導者たちの証言を検証すると、1世紀の奇跡的な賜物は消滅し、もはやキリスト信仰を確立するために必要とされなくなったことが明らかである。さらに、これらの賜物が存在していたとしても、それに反する多くの証言があるにもかかわらず、それは広範囲にわたるものでもなく、通常のクリスチャンの経験でもなかったことがはっきりしている。
このような現象に類する唯一の明確な言及は、異端者モンタヌスとその誤った霊の理解に影響を受けた者たちに関連するものである。これら全ての証拠は、パウロが「異言はやむ」(Ⅰコリント13:8)と預言した言葉が真実であったことを示している。
出典
The Gift of Tongues in the Post Apostolic Church (A.D. 100-400)
Bibliotheca Sacra Vol.122 (Apr 1965)
Cleon L. Rogers, Jr.