患難期前携挙説への
よくある反論
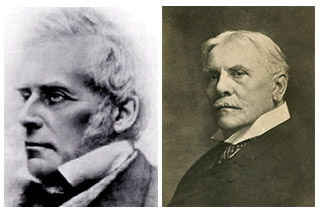
1「患難期前携挙説は歴史の浅い新説ではないか」
患難期前携挙説を否定する者たちが、必ず、真っ先に挙げるのが、患難期前携挙説は歴史が 浅いという点です。彼らは、J・N・ダービー(1800 ~1882 年)以前には、患難期前携挙説は 知られていなかったと言います。しかしそれは全く根拠のない作り話です。患難期前携挙説を教理として体系化するにあたって、ダービーが多大な功績を果たしたのは事実ですが、しかし決して、ダービーは彼独自でこの教理を作り上げたのではありません。
ヘルマスの牧者
95~150年頃に書かれたこの文章は、古代版天路歴程といった感じの物語です。この話の中に、クリスチャンが患難時代を通らないことを示唆する一文があります。
あなたは、あなたの信仰によって、大いなる患難から逃れることができました。あなたは、あのように巨大な獣を見ても、疑わなかったのですから。ですから、行って、主に選ばれた人々に、主の大いなる業を説明してあげなさい。そして彼らに、この獣が来たるべき大いなる患難の予型であると話しなさい。もしあなたがたに備えがあり、主に対して全心から悔い改めるならば、あなたがたはこの患難を免れることができるでありましょう。
イレナエウス(140~202年頃)
リヨンの監督であったイレナエウスは明確に、大患難前に教会が取り去られることを教えています。
そこで、終わりの日に教会が突然この地から取り上げられるとき、「世の初めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が始まる。」と言われているのである。
ヴィクトリヌス(?~303年)
三世紀に活躍したヴィクトリヌスの黙示録注解が今日残っています。残念ながら注解は正確ではありませんが、注目すべきは、6章14節の注解が、患難期前携挙を示していることです。
「天は、巻き物が巻かれるように消えてなくなり」とは、教会が取り去られることである。「すべての山や島がその場所から移された」とは、最後の迫害において、すべての者がその場所から離れることである。すなわち、迫害を避けるために、善人は移されるということである。
シリアのエフレム(306年頃~373年)
エフレムは、「終わりの時と反キリストと世の終局」と題する重要な文章を残しています。そこで明らかに、患難時代前の携挙を述べています。
すべての聖徒たちと神に選ばれた者らは、来るべき患難の前に集められ、主のもとに取られる。それは、我々の罪ゆえに世を覆う混乱を、彼らが見ることのないためである。
以上は初代教父たちの教えですが、これらを読むなら、患難時代前の携挙という考えが、決してダービーの創作ではないことが分かります。初代教会の指導者たちも、クリスチャンたちがこの世から取り去られ、その後に患難の時代が来ると教えていたのです。その後に、教会がローマ帝国の支援を受け、国家的宗教となるにつれ、終末についての正しい教えは語られなくなりました。しかし、カトリック教会の衰退と共に、聖書が母国語に翻訳され、研究されるようになり、再び、終末についての正しい教えが発見され、教えられるようになったのです。
2「『世にあっては患難がある』と主は言われたではないか」
「わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を持つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。」(ヨハネ16章33節)
主イエスは弟子たちに、「あなたがたは、世にあっては患難があります」とおっしゃいました。そして、そのお言葉の通り、クリスチャンたちは世にあって患難を経験してきました。それは使徒の働きの記事や、教会史が証明しているとおりです。また、今日に至るまで、真実にキリストを信じ、従う者たちは、聖書の真理から離れた教会から、また、社会主義やイスラム主義の政府から、さらに、不敬虔な独裁者たちから迫害されてきました。
しかしこれらの迫害は、悪魔に支配された世が、クリスチャンに与える患難です。ですから主イエスは次のように語られました。
「もしあなたがたがこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなたがたは世のものではなく、かえってわたしが世からあなたがたを選び出したのです。れで世はあなたがたを憎むのです。」(ヨハネ15章19節)
しかし、患難時代は、神がこの世に怒りを下される時です。同じ「患難」という言葉が使われていても、誰に対する誰からの患難かが全く異なります。今の時代、クリスチャンに対する世からの患難はありますが、将来の、この世に対する神からの患難の時は、クリスチャンと無関係です。次のみことばは、来るべき患難時代が、世に対する神からの怒りの時であることを明瞭に示しています。
地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ほら穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。「私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と小羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。だれがそれに耐えられよう。」(黙示録6章15~17節)
彼は大声で言った。「神を恐れ、神をあがめよ。神のさばきの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。」また、第二の、別の御使いが続いてやって来て、言った。「大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不品行のぶどう酒を、すべての国々の民に飲ませた者。」(黙示録14章7、8節)
主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け。主の日を。勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、やみと暗黒の日、雲と暗やみの日、角笛とときの声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。 わたしは人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。 彼らの血はちりのように振りまかれ、彼らのはらわたは糞のようにまき散らされる。 彼らの銀も、彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。そのねたみの火で、全土は焼き払われる。主は実に、地に住むすべての者をたちまち滅ぼし尽くす。(ゼパニヤ1章14~18節)
この世に置かれてはいても、この世に属さない、キリストの花嫁である教会は、来るべき患難の時代を通ることはありません。それは、神の怒りの時という患難時代の性格を考えるときに、また、キリストの花嫁であるという教会の身分を考えるときに、明らかです。次のみことばは、クリスチャンが患難時代を通ることがないことを、確証しています。
神は、私たちが御怒りに会うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。(第一テサロニケ5章9節)
3「患難時代の前に聖霊が取り去られるなら、患難時代に人は救われ得ないではないか」
テサロニケ人への手紙第二の2章6節と7節に次のように記されています。
(6節)「そして、彼が彼の時に〔彼に決められた時に〕現れるように、今は(彼を)引き止めているものがあることをあなたがたは知っています。」
(7節)「しかし、今すでに無法の秘密は働いています。ただ、それはその引き止めている者がその役から身を引かされる時までです。」
この「引き止めているもの」は、クリスチャンたち、あるいはクリスチャンたちを通して働かれる聖霊と、一般的に理解されています。そこで、患難期前携挙に反対する人々は、こう反論します。「もしも患難時代の前に聖霊が取り去られるとすれば、魂の救いは聖霊の働きによるのであるのだから、その聖霊不在の中、どのようにして人々が救われるのか。聖書は患難時代においても、救われる者があると語っているではないか。」
このように反論をする人たちは、まず、聖書が、聖霊が取り除かれるとは語っていないことを知るべきです。第六節の「引き止めているもの」は〔 ト カテコン〕の訳です。「ト」は中性単数の冠詞です。これは聖霊を意味しています。ギリシア語では聖霊は通常中性で表現されています。しかし、第七節の「その引き止めている者」は〔 ホ カテコーン〕の訳で、「ホ」は、男性単数の冠詞です。ですから〔 ト カテコン〕は聖霊御自身ではないのです。それは、聖霊によって形成された、偽キリストの出現を止める力がある個人か、団体を意味しています。この聖句の前後関係から見て、これは「個人」ではあり得ません。ですから、それは団体と取るべきです。教会は、キリストとの関係においては通常女性で表現されていますが、世の悪の力に対して戦いながら福音を宣べ伝えている「団体」という意味での教会を男性名詞で表現していると取ることが最も文脈に相応しいのです。
新改訳聖書が「取り除かれる」と訳している言語は〔 エ ク メソウ ゲネタイ〕なのです。この句をギリシア語の表現の習慣を無視して、下手な日本語に直訳すると「真ん中からいなくなる」となるのですが、ギリシア語の表現の習慣に従えば「主役でなくなる、役から外される」となるのです。ですからエマオ訳では「その役から身を引かされる」と訳されているのです。教会は、無法の男、すなわち偽キリストが世に現れるべき時が来るまで偽キリストの出現を止めているのですが、患難時代が始まる前にその止める働きから身を引かされるのです。(聖霊が世から天に引き上げられるのではありません。)教会は患難時代が来る前に天に引き上げられます。そして、地上に教会が存在しなくなってから、偽キリストは世に出て来るのです。
今の教会時代は、聖霊が信者に内住され、信者をキリストのからだにバプテスマされるという、旧約の時代とは異なる聖霊の働きが行われている時代です。そして現在、聖霊は教会を通して福音伝道の働きを行っておられます。しかし、旧約の時代においても、聖霊は働いておられ、その働きによって救われる人々が起こされたのです。教会時代の後においても、イスラエル人の中の「残りの者たち」を通して聖霊の働きは続けられ、救われる者は起こされます。
4「再臨に関して使われている三つのギリシア語は、携挙と地上再臨とを区別していない」
これは次のような議論です。
(1)再臨を表すギリシア語は三種類ある。すなわち、「パルーシア」「アポカリプシス」「エピファネイア」である。
(2)しかし、これら三つの用語は、それぞれ、ディスペンセイション主義者が携挙を指すと言う聖句にも、地上再臨を指すと言う聖句にも使われている。
(3)従って、聖書は携挙と地上再臨とを区別していない。
ディスペンセイション主義に強固に反対するG・E・ラッドは、この議論を長々と展開しています。(The last things p.49-57) それゆえ、ラッドと同じ立場に立つ者たちは、必ずと言っていいほど、この議論を使います。しかし、この議論は、証明されていない前提に立つ議論です。すなわち、もしも聖書が携挙と地上再臨とを区別しているなら、それぞれに別の用語が用いられているはずだという前提です。しかし、この前提こそが間違っています。たとえば、「パルーシア」という語は、「到来、来臨、出現、着席」などを意味する語です。なにも携挙だけを特定している語というわけではありません。「パルーシア」は、第一テサロニケ4章15節では「再び来られる」と訳されており、第二テサロニケ2章8節では「来臨」と訳されています。同じ用語が使われていますが、どのような「到来、来臨、出現」であるかを決定するのは文脈です。第一テサロニケ4章15節では、主イエスが空中に到来、来臨、出現されることを意味しており、携挙を指しています。しかし、第二テサロニケ2章8節は、不法の人(偽キリスト)を御口の息をもって殺すために、到来、来臨、出現されることを意味しており、地上再臨を指しています。
実のところ、パルーシアは、何も主の来臨だけに限って用いられている用語ではなく、第二テサロニケ2章9節では、「不法の人の到来(パルーシア)」と、偽キリストの到来に関しても用いられています。ですから結局のところ、この議論は、携挙と地上再臨とが別の出来事であることを否定することもできないし、携挙と地上再臨が同じ出来事であることを証明することもできません。
5「第一テサロニケ4章17節の『会う』は『出迎えて、すぐに戻る』という意味だ」
まず、第一テサロニケ4章17節を引用します。
次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。
問題となるのは、「会う(アパンテーシス)」です。患難期前の携挙を否定する者たちの議論はこうです。「この、アパンテーシスという語は、使徒の働き28章15節では、ローマのクリスチャンたちがパウロを出迎えに行った場面でも用いられている。彼らがパウロに会い、一緒にローマに戻って来たように、クリスチャンが携挙されたなら、彼らは主とともに直ちに地上に戻って来るのである。従って、主の再臨はただ一度だけで、それは患難時代の最後に起こるのである。」これもラッド以来、ディスペンセイション主義に反対する者たちが、よく使う論法です。
この議論に対する反論は、シーセンの組織神学から引用します。
この言葉(アパンテーシス)の出てくる箇所が他に二つある。すなわち、マタイ25章6節と使徒の働き28章15節である。しかし、どちらの場合も、会ってすぐ後でもどって来たということは、明らかではない。パウロは、ローマに出発する前に、彼に会いにやって来た兄弟たちと、確かに交わりの時をもったはずである。ここで用いられているギリシア語「アパンテーシス」は、単なる会見を意味し、同じ語源から来るギリシア語の動詞「アパンタオー」は、会いに行く、会うを意味する。事実、公認本文によるルカ14章31節の読み方、七十人訳による第一サムエル22章17節、第二サムエル1章15節、第一マカベア11章15節と68節、および他のギリシア語の著作においても、戻って来るという思想を見いだすことは不可能である。そこで我々は、キリストはご自身の民とともに帰られるが、その用語はどこまでも、直ちに戻られるとは示唆していない、と断言する。」(786頁より)
以上、患難期前再臨説に対する主な批判を取り上げました。ディスペンセイション主義に対する反論が、反論するに値しないほど極めて幼稚で、しかも節度を欠いたものであったので、ディスペンセイション主義者たちはこれまで反論に控えめであったのです。そのために彼らはディスペンセイション主義を完全にノックアウトしたと早合点をしているようです。読者が聖書から冷静な判断を下されるように願います。(エマオ出版 終末論 323~335頁より)


